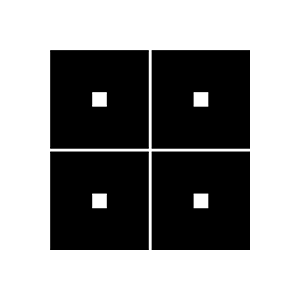
京極家の家紋「平四つ目結」
| 別称 | 舞鶴城 |
|---|---|
| 築城 | 1582年 |
| 住所 | 京都府舞鶴市南田辺15-22 |
| 電話番号 | 0773-76-7211 |
| 開館時間 | 9:00〜17:00(入館は16:30まで) |
| 休館日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌々日)、祝日の翌日、年末年始(12/29~1/3) |
| 登閣料 | 大人200円/学生100円 |
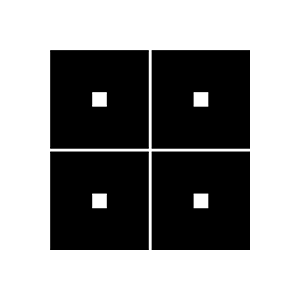
京極家の家紋「平四つ目結」
| 藩庁 | 田辺城 |
|---|---|
| 旧地域 | 丹後国 |
| 石高 | 3万5000石 |
| 譜代・外様 | 外様・譜代 |
| 主な藩主 | 京極家、牧野家 |
京都府舞鶴市にあった田辺城は、天正年間に細川幽斎が築いた平城です。城が南北に長く、近くの峠から眺めると鶴が舞っているように見えることから「舞鶴城」とも呼ばれ、「舞鶴」の地名の由来になりました。関ヶ原の戦いの前哨戦として、西軍を前に細川幽斎が少数で籠城戦を繰り広げた「田辺城の戦い」の舞台として知られています。現在は大手門や隅櫓が再建されています。










