高天神城の戦い武田vs徳川の遠江攻防戦
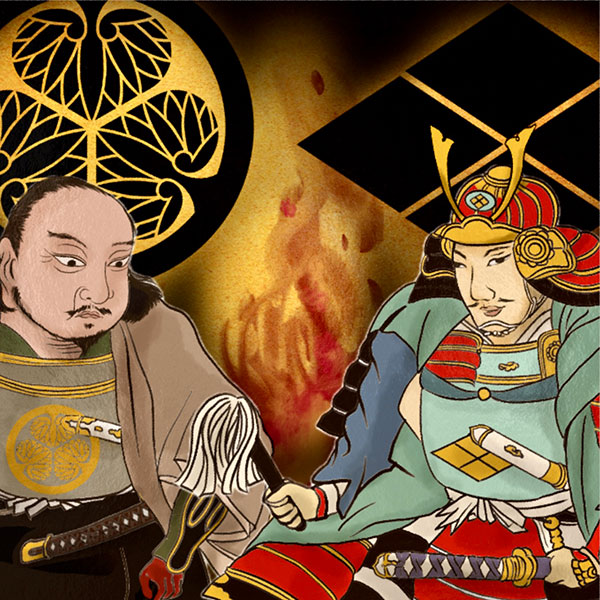
高天神城の戦い
遠江国(現静岡県西部)の要衝・高天神城(静岡県掛川市)は、「高天神を制する者は遠州を制す」と言われるほど重要な拠点でした。このため戦国時代には、高天神城をめぐって武田氏と徳川氏が激しい覇権争いを繰り広げました。なかでも天正2年(1574年)と天正9年(1581年)の二度にわたって繰り広げられた徳川家康vs武田勝頼の「第一次/第二次高天神城の戦い」は有名です。今回はそんな高天神城をめぐる戦いについて、分かりやすく解説します。
「遠江の要衝」高天神城とは
高天神城は、遠江国と駿河国(静岡県中部)の国境付近にある標高132mの鶴翁山上にある山城です。太平洋岸と遠江北部を結ぶ軍事・交通の要衝に位置し、3方向が断崖絶壁という、難攻不落の城でした。その特徴は「一城別郭」で、東峰と西峰に独立した2つの曲輪がそれぞれ中心となり、東西は中央の井戸曲輪で繋がっています。
高天神城の起源は諸説ありますが、今川氏家臣の福島氏が築いたとされています。福島氏が没落すると、今川氏の重臣・小笠原氏が城代となりました。
当時、今川氏は今川義元の元、駿河・遠江・三河(愛知県東部)の三国を支配していました。ところが永禄3年(1560年)5月の「桶狭間の戦い」で義元が織田信長に討たれると、今川氏は没落し、その領地をめぐり、多くの戦国大名が戦いを仕掛けます。このうち三河国は信長と同盟を結んだ徳川家康が掌握しました。
永禄11年(1568年)、甲斐国(山梨県)の武田信玄が駿府への侵攻を開始(駿府侵攻)すると、家康は武田氏に呼応して遠江を攻めます。今川義元の跡を継いだ今川氏真は「掛川城の戦い」で敗退し、今川氏は事実上滅亡しました。今川氏に仕えていた高天神城の小笠原氏は、徳川家康に仕えるようになりました。
武田信玄による「幻」の高天神城攻め
こうして遠江は徳川領となりましたが、甲斐国の武田信玄はさらに領土を拡大しようと考え、徳川氏と武田氏は敵対するようになります。
通説によれば元亀2年(1571年)2月、武田信玄は遠江に侵攻し、2万の大軍を率いて高天神城を包囲しました。3月には城の南東にある塩買坂(静岡県菊川市川上)に到着し、陣を敷きましたが、獅子ヶ鼻(静岡県菊川市大石)と国安川で小競り合いを行っただけで戦闘は終了。高天神城の強固な守りに手を出せず諦めたと言われています。この時高天神城側は城主の小笠原氏助以下2000の兵のみでした。
ただし、この「信玄による高天神城攻め」についてはその後の研究や発掘調査の結果、戦い自体がなかったのではとされています。
信玄が「西上作戦」で遠江侵攻
元亀3年(1572年)10月、武田信玄は「西上作戦」を開始し、遠江・三河に侵攻します。この際高天神城と家康の本拠地である浜松城を結ぶ二俣城(静岡県浜松市天竜区)が信玄により落とされたため、高天神城は孤立してしまいました。
西上作戦の結果、遠江で武田氏の勢力が拡大しました。ちなみに、この西上作戦の時に起こったのがかの有名な「三方ヶ原の戦い」で、徳川軍は武田軍に大敗しています。
その後、武田軍は三河に侵攻しますが、信玄の病状が悪化したことで撤退。元亀4年(1573年)4月に信玄は没し、その跡を継いだ武田勝頼が父の遺志を継ぎ、遠江攻略を続けることになったのです。
第一次高天神城の戦い、勝者は武田軍
天正元年(1573年)、武田勝頼は遠江攻めの準備として、榛原郡金谷(静岡県島田市金谷)に諏訪原城を築城します。そして天正2年(1574年)5月、2万5000の兵とともに高天神城攻めを開始しました。対する高天神城は城主・小笠原氏助と1000名の兵のみでした。
氏助から救援を求められた徳川家康でしたが、十分な兵力がなかったこともあり、織田信長に救援を求めます。しかし、当時信長は石山本願寺と長島一向一揆との総力戦の最中でした。援軍をそう簡単には送れません。
そうこうしているうちに武田軍は傾斜が緩やかな西峰から攻め込みます。その結果、6月11日時点では本丸と二の丸を残すのみとなっていました。兵糧不足のなか、氏助は6月17日に城兵の助命と、1万貫の所領安堵の条件と引き換えに城を開城しました。こうして高天神城は陥落し、城は武田氏の支配下に入りました。
実は、織田軍の援軍は6月14日には何とか援軍を整え、岐阜城を出発していました。ところが援軍は間に合わず、信長は家康に見舞金のような形で黄金の入った革袋を2つ、兵糧代として贈っています。
なお、この開城に一人だけ応じなかったのが、軍監を務めていた大河内政局でした。政局は城の明け渡しに唯一反対したため、武田軍に捕らえられ、石窟に幽閉されてしまいました。
城を得た勝頼は将兵を助命し、武田方に下ることを希望した武将を召し抱え、徳川方に帰還を望んだ武将に対しては退去を許可しています。この際、小笠原氏助は「信興」と名を変え、武田氏の元で高天神城をしばらくの間治めました。こうした勝頼の寛大な処置は、勝頼自身の名声を高めました。
さらに高天神城を得た武田勝頼は、城の改修に着手します。これまでの高天神城は東峰を中心としていましたが、自らが攻め落とした経験を踏まえ、西峰を改修しました。二の丸の周囲に小さな曲輪を置き、堂の尾曲輪、井楼曲輪を重ね、堀切で分断し、横堀や土塁を巡らせるなど、防御力を高めたのです。なお、この頃小笠原信興に変わり、城番として横田尹松が入っています。
長篠の戦いで武田軍が大敗
第一次高天神城の戦いで遠江の主導権を握った武田勝頼。次は徳川家康の本拠地である三河攻略に乗り出します。天正3年(1575年)5月、長篠城(愛知県新城市)を1万5000の大軍で攻めたのです(長篠の戦い)。
対する織田・徳川連合軍は3万8000人。勝頼と決着をつけようと大軍を投入し、入念な準備で武田軍を迎え撃ちました。その結果、武田軍は織田・徳川連合軍に大敗してしまいます。さらに、山県昌景や馬場信春、土屋昌次といった重臣を失ってしまいました。
以後、徳川軍は着実に遠江南部の諸城を奪還し、武田方の支配はじわじわと後退していくことになります。
第二次高天神城の戦い①家康が補給路を絶つ
長篠の戦いで勝利をおさめた徳川家康は、高天神城を奪還しようと策を練ります。とはいえ、武田方が改修し、より堅城となった城をすぐに奪還するのは難しいとも考えていました。このため、家康はまず、武田信玄の西上作戦の際に奪われた二俣城の奪還に取り掛かります。二俣城は堅城なので、周辺に城や砦を築いて長期戦に備えました。
それと同時に、家康は光明城(静岡県浜松市天竜区)等の城を次々と攻略。そしてついに高天神城の補給拠点である諏訪原城攻めに乗り出し、これを落としました。長篠の戦いで敗れた武田軍が動きを止めていることを好機と考えた家康は、こうして次々と武田方の城を落としていったのです。なお、諏訪原城にいた武田軍は近くの小山城(静岡県榛原郡吉田町)に撤退しています。
さらに家康は高天神城の抑えとして、天正8年(1580年)8月頃までに「高天神六砦」と呼ばれる火ヶ峰砦、小笠山砦、能ヶ坂砦、獅子ヶ鼻砦、三井山砦、中村(山)砦を順次築城(一部の砦は既存のものを改修)し、武田方から高天神城への物資の補給路を断ちました。武田方は小山城や、水運ルートで物資を補給するはずが、六砦が邪魔をしたためうまくいかず、高天神城はやがて孤立していきます。
その一方、家康は天正6年(1578年)頃に横須賀城を築城して対高天神城の最前線としました。遠州灘につながる潟湖の入口に位置する城は、物資の集積や水運の統制拠点として機能しました。
第二次高天神城の戦い②武田軍を兵糧攻め
高天神城が徐々に孤立していくなか、徳川家康は天正8年(1580年)10月、高天神城を5000の軍で包囲します。といっても直接攻撃するのではなく、家康は高天神城の周囲に堀や塀、鹿垣などを作り、高天神城に出入りできなくしたのです。さらに家康は補給線を絶ち、高天神城を兵糧攻めにしました。
このとき高天神城には武田家臣の岡部元信が約700人を率いて籠城していました。元信はもともと今川氏の重臣で、桶狭間の戦いの際大奮戦したことで知られています。元信は武田勝頼に救援要請を行いました。
しかし、当時の勝頼は、長篠の戦いによる敗戦で財政的に厳しい状態にありました。外交的には北条氏と結んだ「甲相同盟」が断絶し、駿河国東部で北条氏政と敵対していました。これは天正6年(1578年)、上杉謙信死後に起きた跡継ぎ争いの「御館の乱」で、氏政と勝頼が対立したことが原因でした。さらに勝頼は信長と和睦を検討していたようで、高天神城に援軍を出すと信長を刺激するのでは…という恐れがあったともいわれています。
また、高天神城にいた軍監の横田尹松からは密かに「武田軍の兵力を温存するため、高天神城は見捨てるべき」という内容の書状も届いていました。内部からみても、救援がきても厳しいと感じていたのかもしれません。こうした要因もあり、結局勝頼は高天神城の救援を諦めました。
第二次高天神城の戦い③最後の戦い
天正9年(1581年)、待てど暮らせど救援が来ない中、高天神城の兵士たちは独自に動くことを決めます。まずは徳川方に向けて降伏したい旨を記した矢文を送りました。内容としては「降伏し、高天神城・小山城・滝堺城を開城するので、城兵の命を助けて欲しい」というものでした。しかし、徳川家康はこれを拒否。このまま兵糧攻めを続ければ勝てるわけですし、勝頼が出てこないことはわかり切っていたからです。
さらに、織田信長からも、家臣の水野忠重経由で家康に対し、勝頼はどうせ出陣しない、3つの城を勝頼が見捨てれば駿河は手に入るだろう、という趣旨の書状が届いていました。結局家康も信長も「勝頼が援軍を送れない」ということを正確に見切っていたわけです。
籠城した多くの兵士たちが餓死するなか、3月22日、岡部元信は城から討って出ることを決意。900名あまりの兵士が玉砕覚悟で徳川軍に突撃しますが、激戦の末討ち取られました。武田方の死者は730名余りで、遺体で堀が埋まる勢いの壮絶な戦いだったようです。
その後、高天神城は落城。家康は捕らえた兵のほとんどを処刑するという、第一次高天神城の戦いの勝頼とは真逆の厳しい対応をしました。理由としては、他の武田方の武将たちへの示威行動だったとも、勝頼の威信を低下させるためだったからだとも言われています。
こうして家康は城郭を焼き払って浜松城へ帰り、城は廃城となりました。なお、この際第一次高天神城の戦いでつかまっていた大河内政局が7年ぶりに発見され、救出されています。
第二次高天神城の戦い④横田尹松の大脱出
高天神城の武田軍が決死の思いで討ち死にするなか、こっそり城を脱出していた人物がいます。それが軍監の横田尹松でした。
尹松は落城の際に徳川方の旗を拾い、徳川方の目を盗み、現在は「犬戻り猿戻り」「甚五郎抜け道」と呼ばれる尾根続きの隘路を伝って逃げ延び、甲府の武田勝頼の元まで辿りつき、落城の様子を伝えました。勝頼は無事に戻ってきた尹松を誉めて褒美を与えようとしましたが、尹松は「負けて帰って褒美を貰うのは筋違い」と辞退しています。
ちなみに尹松は武田氏の滅亡後、なんと徳川方に下り、家康のもとで関ヶ原の戦いや大坂の陣に従軍。江戸時代まで生き延びています。
武田氏滅亡へ
第二次高天神城の戦いの敗北により、武田軍の士気は大きく下がりました。援軍を出さなかった武田勝頼は求心力を低下させ、家臣たちの離反を招きました。結局天正10年(1582年)2月、織田信長は甲州征伐を実施。合わせて徳川家康や北条氏も武田氏を攻めました。そして3月11日、勝頼は天目山の戦いで自害し、甲斐武田氏は滅亡しました。

- 執筆者 栗本奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。




