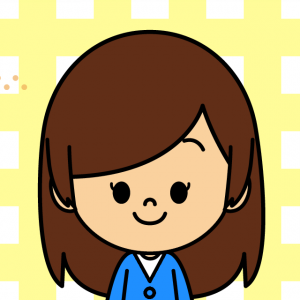徳川家光江戸幕府を盤石にした3代将軍

徳川家光
戦国時代が織田信長の死後、豊臣秀吉によって天下統一されるも、死去すると跡取りだった豊臣秀頼がまだ幼かったこともあり、再び天下が揺れます。1600年に関ヶ原の戦いで徳川家康が勝ち、江戸幕府が開かれ、その3代目将軍として天下を治めたのが徳川家光です。
今回は、3代目の征夷大将軍として様々な施策を実行に移して幕府の基盤を盤石にし、後進に譲った家光の生涯について紹介します。
誕生から世継ぎ決定まで
慶長9年(1604)7月17日、江戸幕府2代将軍だった徳川秀忠の次男として江戸城西の丸で誕生しました。母は太閤豊臣秀吉の養女・達子(浅井長政の三女)、お江の方としての名前の方が知られているかもしれません。
徳川家の世継ぎであった父・秀忠には慶長6年(1601)に誕生した長男・長丸がいました。しかし、当時は衛生水準や医療が発達していなかったこともあって、家光が生まれた頃には既に早世していたこともあり、世継ぎとして扱われます。
そのため、偉大な祖父・家康と同じ幼名「竹千代」を与えられました。誕生に伴って、明智光秀家臣・斎藤利三の娘である福(小早川家家臣稲葉正成室、後の春日局)が乳母となり、稲葉正勝・松平信綱・岡部永綱・水野光綱・永井直貞らの小姓が付けられます。
そして、慶長10年(1605)、家康は隠居、秀忠に将軍職を譲って大御所となりました。
幼少時の家光は病弱だけでなく吃音があり、容姿も美麗とは言えなかったと言われています。そのために、慶長11年(1606)に弟・国松(後の忠長)が誕生すると、竹千代と国松の間には世継ぎ争いがあったとも言われています。
『武野燭談』の記録によれば、当時秀忠や母・お江の方たちは弟の忠長を寵愛しており、竹千代廃嫡の危機すらあったと伝わります。廃嫡の危険を感じた春日局は、駿府で隠居していた大御所・家康に実情を訴え出るという行動に出ます。
春日局から話を聞き、跡目争いがおこることを憂慮した祖父・家康が秀忠たちの下に立ち寄った際、無邪気に本来は家光が座るべき席に座ろうとし、家康の膝に乗ろうとした国松を一喝。公衆の面前で竹千代(家光)と国松(忠長)の長幼の序列を明確にして、竹千代が世継であることを明確にし、お江の方や秀忠にくぎを刺したと言われています。
この件があり、世継ぎの座が正式に決定が確定したと言われていますが、これらの話はすべて家光死後に成立した巷説です。
ただ、同時代史料の検討が進み、現在では家光が世継ぎとして正式に決定したのは、元和年間であると考えられています。
成人そして婚姻
元和2年(1616)5月には、竹千代の守役として酒井忠利・内藤清次・青山忠俊の3人が家光付けの年寄となり、9月には60数名の少年が小姓として任命されます。こうして、家光の年寄衆・家臣団が形成されていきました。
元和3年(1617)には西の丸へ移り、元和4年(1618)には朝廷の勅使を迎えており、公式の場への出席した形跡が見られます。元和2年(1616)の家康の死去によって延期されていた元服は元和6年(1620)に執り行われ、名前も幼名の竹千代から家光へと改めます。同時に、朝廷から従三位権大納言に任命されました。
「家光」の諱は、家康の近くに仕えていた金地院崇伝が選定しています。
崇伝の記した『本光国師日記』には、当初は「家忠」を勘案したものの、平安時代の公卿の左大臣藤原家忠の諱と同じであることを考慮して、あらためて「家光」を選定したいう記録が残っています。
「家」は明らかに家康の「家」を受け継いでおり、以後の徳川将軍家ではこの「家」が嫡男の諱に使用する通字となりました。元和8年(1622)、鎧着初(具足始め)が行われ、具足親は加藤嘉明が務めました。
元和9年(1623)には死去した内藤清次の後任として新たに酒井忠世・酒井忠勝が年寄として付けられました。同年3月5日には、将軍家世子として朝廷より右近衛大将に任じられ、6月には父・秀忠とともに上洛して、7月27日に伏見城で将軍宣下を受け、正二位内大臣となります。
この時、後水尾天皇や入内した妹・和子とも対面しました。
江戸へ戻ると、秀忠は江戸城西の丸に隠居し、家光は本丸へと移ります。将軍となった家光の結婚相手としては様々な候補がいる中、黒田長政の娘との噂もありましたが、元和9年(1623)8月には五摂家の一つ、摂家鷹司家から鷹司孝子が江戸へ下り、同年12月には正式に輿入れして御台所(正室)となりました。
秀忠との二頭政治と父の死去
父・秀忠は将軍職を家光へ譲った後も、祖父・家康と同じように大御所として主に軍事指揮権等の政治的実権は掌握し続けました。そのため、実際の幕政は家光がいる本丸年寄と、父・秀忠がいる西の丸年寄の合議による二元政治という形になります。
家光は将軍になるやすぐに、守役の青山忠俊を老中から罷免し、寛永2年(1625)には改易に処しています(忠俊の子の青山宗俊が後に旗本を経て大名に復帰)。
寛永3年(1626)7月には後水尾天皇の二条城行幸のために再び上洛しますが、将軍・家光に対して大御所・秀忠は伊達政宗・佐竹義宣ら主だった多くの大名、旗本らを従えての大規模な上洛でした。
家光は二条城で後水尾天皇に拝謁し、父・秀忠の太政大臣に対し家光は左大臣および左近衛大将に昇格しました。
寛永9年(1632)1月に父・秀忠が死去すると二元政治は解消されて、家光は実質的に将軍から公方として腕を振るい始めます。
旗本を中心とする直轄軍の再編に着手しつつ、全国に巡見使を派遣して各地の大名の動向など情勢を監察させました。全国規模での巡見使の派遣は家光が初で、同年5月には外様大名を招集し、藩内の内訌などを理由に、肥後熊本藩主・加藤忠広の改易を命じています。
寛永10年(1633)福岡藩における栗山大膳事件(黒田騒動)では自ら裁定を下して藩主黒田忠之の主張を認め、寛永12年(1635)対馬藩における柳川一件でも藩主宗義成の主張を認めるなど、積極的に関与しました。
幕政改革では、老中・若年寄・奉行・大目付の制を定め、現職将軍を最高権力者とする幕府機構を確立しています。同年9月には外祖父の浅井長政に権中納言を贈官。
寛永12年(1635)の武家諸法度の改訂では、大名に参勤交代を義務づける規定を加えています。
こうして、祖父・家康、父・秀忠、そして家光の3代で幕府の基盤が確立したと言えるでしょう。
家光の対外貿易政策
対外的には長崎貿易の利益独占目的と国際紛争の回避、家康から続くキリシタンの排除を目的に、対外貿易の管理と統制を強化していきます。
親政が始まった後、まず長崎奉行の竹中重義に改易と切腹を命じ、新しい長崎奉行を旗本2人から任命して、同時に寛永10年(1633)から寛永13年(1636)にかけて、長崎奉行に東南アジア方面との貿易の管理と統制を目的とした職務規定(鎖国令)を発布しました。
寛永12年(1635)の長崎奉行への職務規定(第三次鎖国令)では、日本人の東南アジア方面との往来が禁止されることになり、宣教師の密航の手段であり国際紛争の火種となっていた朱印船貿易は終焉を迎えました。
同時に、朱印船の役割は外国人(オランダ人・ポルトガル人・中国人)が代行することになり、寛永12年(1635)に九州各地の中国人は長崎のみに居住が許され、ポルトガル人は寛永13年(1636)長崎の出島に隔離されました。
寛永14年(1637)に起きた島原の乱を鎮圧した後、ポルトガルとの断交を決意、寛永16年(1639)に、オランダ商館長のフランソワ・カロンを通して、台湾経由でも中国産の生糸を確保できることを確認。
そのうえで長崎奉行や九州地方の諸大名に対してポルトガル人の追放を命じた命令(第五次鎖国令)を発布しました。寛永18年(1641)にはオランダ商館を出島に移転し、長崎を通じた貿易の管理・統制である「鎖国」体制を完成させています。ただし、「鎖国」という概念や言葉が生まれるのは19世紀になってからであり、当時はあくまでも厳しい隔離という体裁だったようです。
政権の安定と飢饉、死去まで
これら3代将軍・家光の代までに取られた江戸幕府の一連の強権政策は現在では「武断政治」と言われています。
長崎奉行(竹中重義)に切腹を命じたのも、島原の乱の責任を問うとして大名(松倉勝家)を切腹ではなく斬首に処したのも江戸時代で唯一の処置であり、改易でも50万石以上の大名(徳川忠長・加藤忠広)を改易に処した将軍は家光が最後となっています。
寛永18年(1641)には側室・七澤楽子(お蘭/またはお楽の方とも呼ばれる)の間に嫡男の竹千代(後の4代将軍・家綱)が生まれました。
寛永11年(1634)に家光は30万の大軍を率いて3度目の上洛を行い、後水尾上皇による院政を認め、紫衣事件以来冷え込んでいた朝幕関係を再建することで、国内政治の安定を図りました。
ところが幕府の基盤が安定したと思われた矢先の寛永19年(1642)からは寛永の大飢饉が発生、国内の諸大名・百姓の経営は大きな打撃を受けます。更に正保元年(1644)には中国大陸で明が滅亡して満州族の清が進出するなど、内外の深刻な問題が立て続けに起こり、家光は体制の立て直しを迫られました。
正保元年(1644)には全国の大名に郷帳・国絵図(正保国絵図)・城絵図(正保城絵図)を作成させ、農民統制では田畑永代売買禁止令を発布します。
慶安3年(1650)には病気となり、諸儀礼を家綱に代行させ、翌年4月20日に江戸城内で死。享年48。
家光の死に際して、堀田正盛や阿部重次、内田正信らが殉死しています。遺骸は遺言によって東叡山寛永寺に移され、日光の輪王寺に葬られました。
同年5月には正一位・太政大臣が追贈され、法名は大猷院に定められました。翌承応元年(1653年)には大猷院廟が造営されています。
家光と姉弟との仲
前述の通り、家光と弟・忠長は幼少のころから両親(秀忠・お江の方)の愛情が弟に集中したことで微妙であったとも言われます。
家光が将軍就任後、忠長も中納言に任官。寛永元年(1624)には駿河・遠江・甲斐で55万石を領する大大名となり、2年後に従二位権大納言に任官したことから通称「駿河大納言」と呼ばれるようになりました。
御三家の尾張・紀州と肩を並べる官位・所領でした。同寛永3年(1626)、実母のお江がし、 同寛永3年には家光の上洛にも随行するも、家光の行列が便利なようにと、忠長が大井川に船橋を架けたところ、「箱根大井は街道第一の険要であり、関東の障蔽であると神祖(家康)も大御所(秀忠)も常々仰せであるのに、余計なことをする」と家光の怒りを買ってしまいます。この頃から忠長は、重臣たちの諫言に耳を貸さず、大坂への移封や100万石への加増を願うなど、一線を越えた要求が増えていきます。
また殺生禁断の地の浅間山に入ると、人々の制止を振り切って、浅間神社の神獣といわれた猿を1200頭も殺し、「忠長卿狂気」と噂されるに至りました。
寛永8年(1631)、「身のふるまい凶暴にして、去年より罪なき家士数十人を手討ちにせられ、そのさま狂気に類せり」という理由で、忠長は甲府への蟄居を命じられました。
翌年の父・秀忠危篤の際も江戸入りは許されず、父の死に目には会えませんでした。秀忠が死去した後、忠長は全所領没収の上、高崎に蟄居。そして寛永10年(1634)12月、幕府の命により高崎の大進寺で自刃したのでした。
一方で、姉の千姫とは仲が良かったようです。千姫は、豊臣秀頼に嫁ぎ、大坂夏の陣で大坂城を脱出して江戸に戻った後、本多忠政の長男・忠刻と再婚して一男一女をもうけるも、男児は夭折し、さらに夫となった忠刻も死去し、再び江戸へと戻ります。
江戸城内の竹橋御殿に住み、出家して天樹院と称しました。その後、寛永6年(1629)には加賀藩の前田光高との婚儀の話もあったようですが、双方乗り気ではなかったため取りやめとなったようです。
家光は、姉の千姫をことのほか大切にし、江戸城内で穏やかに暮らせるよう気を配っていたとも言われています。

- 執筆者 葉月 智世(ライター) 学生時代から歴史や地理が好きで、史跡や寺社仏閣巡りを楽しみ、古文書などを調べてきました。特に日本史ででは中世、世界史ではヨーロッパ史に強く、一次資料などの資料はもちろん、エンタメ歴史小説まで幅広く読んでいます。 好きな武将や城は多すぎてなかなか挙げられませんが、特に松永久秀・明智光秀、城であれば彦根城・伏見城が好き。武将の人生や城の歴史について話し始めると止まらない一面もあります。